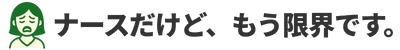看護師は爪切り・巻き爪ケアを事業にするのはOK?資格必要?
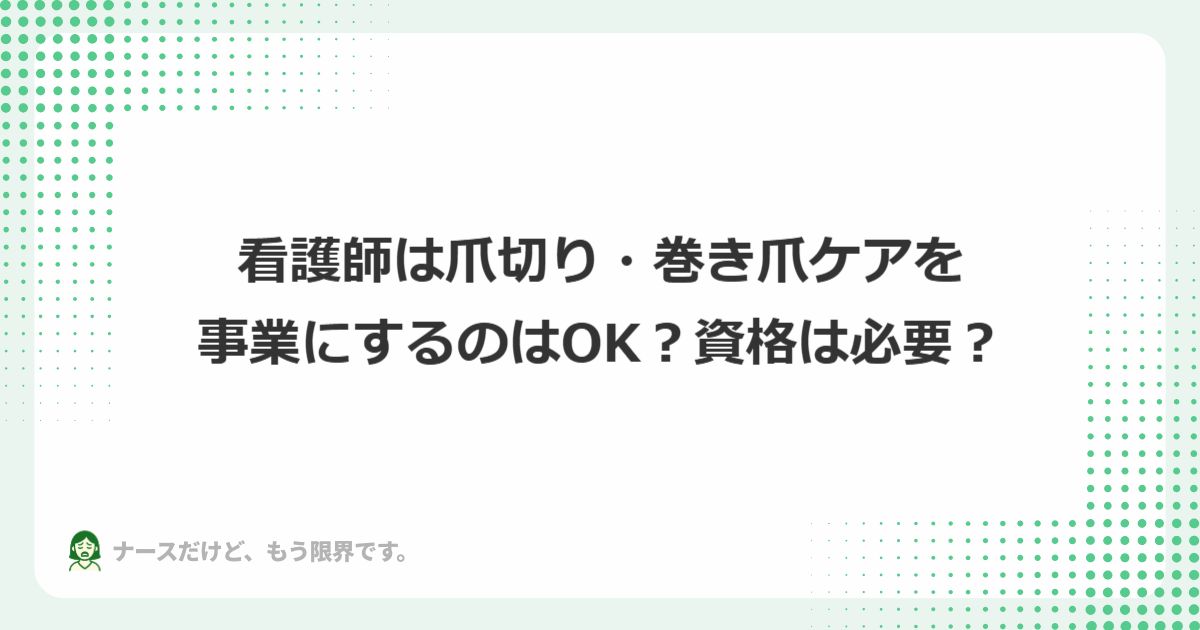
高齢者施設や在宅医療の現場でニーズが高まっている「爪のケア」。特に足の爪は、自分でうまく切れない高齢者や糖尿病患者などにとって、専門的なケアが健康維持に直結します。こうしたニーズに応える形で、看護師が「爪切りサービス」や「フットケア事業」を始めようと考えるケースも増えています。
しかし、実際に事業として爪のケアを行う場合、「医療行為に該当しないのか?」「資格が必要なのか?」といった法的・実務的な疑問が浮かびます。特に医療の現場で経験を積んだ看護師さんや、臨床で色々こなすことに疲れてしまって爪切りなどのライトなケアが喜んでもらえて楽しいという人も一定数いるのではないでしょうか?
この記事では、看護師が爪切りや巻き爪のケアを提供することは可能なのか、必要な資格や注意点について詳しく解説します。
爪切りや爪のケアは医療行為にあたるのか?
まず押さえておきたいのは、「爪切り」や「簡単なフットケア」は、原則として医療行為には該当しないという点です。つまり、看護師でなくても、誰でも行うことが可能です。たとえば、介護職員が介護施設で入所者の手足の爪を切ること、家族が高齢者の爪を整えること、訪問理美容でネイルケアを行うことなどは、すでに日常的に行われている業務です。
ただし、以下のような行為になると注意が必要です。
こうした行為は、医師の指示のもとでしか行えない「医行為」に該当する可能性があります。看護師であっても、単独でこうした処置を業務として行う場合には医師法違反に問われるリスクがあります。
一方で、医師とタッグを組んで指示や医学的管理の下で爪ケアを行うならば、難しい爪の状態にも対応ができ、爪で悩んでいる人のニーズにも応えられる可能性があります。
介護職員の爪切りも医療行為には当たらないと厚生労働省が示している
厚生労働省は「令和6年度老人保健健康増進等事業 原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」の中で、「爪の切り揃え(皮膚疾患や爪の病変のない場合に限る)」は原則として医療行為には当たらない具体例として示しています。
参考:2025年版 医行為ではない具体例、介護職員ができること(介護健康福祉のお役立ち通信)
看護師資格があれば爪切りの事業ができるのか?
看護師であることは「医療職としての信用」につながる要素ではありますが、爪のケアそのものが医療行為でない場合には、看護師資格が必須というわけではありません。実際、介護職や理美容師などもフットケア事業を行っています。
しかし、看護師ならではの強みもあります。たとえば、以下のような点です。
これらは「ただの爪切り」以上の安心感を提供し、利用者から高く評価されやすく、事業の差別化にもつながります。
民間資格は必要か?取得する意味とは
爪ケアに関する民間資格は複数あります。
たとえば・・・
これらの資格は法律上の業務独占資格ではないため、無資格でも爪切りやフットケアの提供は可能です。しかし、次のような観点で取得するメリットがあります。
特に医療行為との境界があいまいな「巻き爪ケア」や「フットバス+ケア+保湿」といったセットメニューを組む場合には、体系的な学びを得ておくことは大きな意味を持ちます。
巻き爪矯正(ワイヤー法)は看護師がやってもOK?
巻き爪ケアの代表的手法として知られる「ワイヤー法(爪に穴をあけ、形状記憶合金などのワイヤーを通して矯正する)」は、医療機関でも導入されていますが、この行為自体が医療行為に当たるかは非常にグレーゾーンです。
2023年時点の厚生労働省の公式見解では、「爪への穴あけやワイヤーの挿入」が直接的に医行為に該当するという明確な通達は出ていません。しかし、皮膚や爪を損傷させるリスク、痛みや出血を伴う可能性があることから、万が一顧客に怪我をさせてしまった場合には、「業務上過失傷害」に問われる可能性があります。
看護師であっても、事業としてこの技術を提供する場合には、事前に医師の監修のもとで業務を整理する、またはリスク説明と同意書の取得、賠償責任保険の加入など、リスクマネジメントを徹底することが不可欠です。
開業・自費サービスとして始めるときのポイント
爪切りや爪のケアを個人事業として始める看護師も増えています。特に高齢者施設や在宅介護を受けている家庭では、「爪だけ切ってくれる人がいない」「通院ができない」という切実なニーズがあります。こうした背景から、訪問爪ケアや出張フットケアの需要は年々高まっています。
開業にあたっては、医療行為をしないことを明確にし、サービスの範囲・料金・リスク説明を契約書や同意書として整備する必要があります。また、業務用消毒や衛生管理の徹底、事故があった場合に備えた損害保険の加入も重要です。
多くの成功事例では、介護施設との提携や訪問看護ステーションとの連携を図ることで、定期的な訪問先を確保し、収益の安定化に成功しています。
爪ケア専門店を毎日営業するわけではなく、インスタやホームページなどで定期的に発信をして集客を行い、週末だけや依頼があった時だけなどという働き方もできるので、看護師としてのお勤めをほどほどにして、副業やライフワークとして爪切りを行っていくというのもありだと思います。
まとめ
爪のケアは、医療行為ではなくても人々のQOLに直結する重要なケアの一つです。看護師がこれを自費サービスとして提供することは、制度的にも可能であり、地域の中で新たな役割を果たす選択肢ともいえます。
ただし、医療行為との線引きが曖昧な部分もあるため、業務範囲や手技内容については慎重に設計し、必要に応じて民間資格を取得することで知識やリスク対応力を高めておくことが望まれます。資格そのものが義務ではありませんが、実務での信頼性や安全性の確保という点では、取得の価値は十分にあります。
高齢化が進む中、爪のケアを通じて社会貢献ができるこの分野は、看護師にとって新たな働き方の可能性を広げるフィールドです。