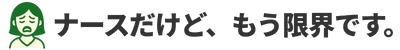高齢者で認知症でも選挙で投票できるって…付き添いや代理投票までやるって正気?
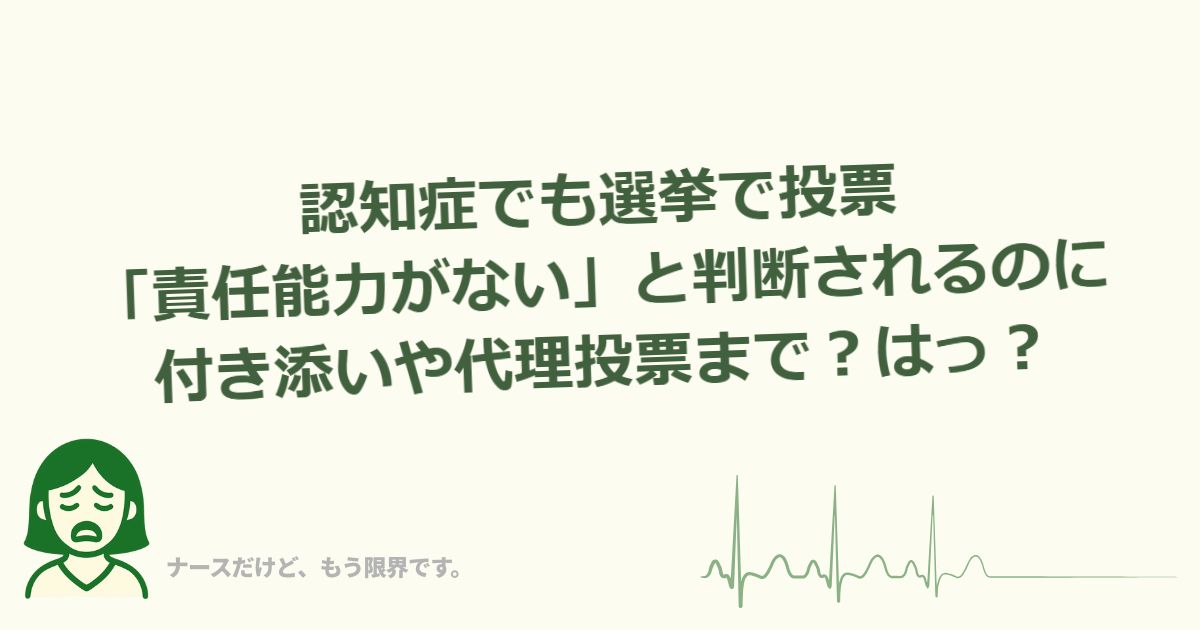
近年、急速に進む高齢化に伴い、認知症の有病率も増加しています。一方で、認知症や精神疾患を抱える人が事故やトラブルを起こした場合には「責任能力がない」と判断され、刑事責任や民事責任を問われないケースも珍しくありません。ところが、選挙の場になると一転、そうした人々にも「投票権」が保障され、実際に投票所に足を運び、場合によっては家族や職員の付き添い、さらには「代理投票」まで可能となっているのが現状です。
誰かの人生や財産を左右する場面では「判断能力の欠如」が問題視されるのに、国家の進路を左右する選挙では問われない――この矛盾に違和感を覚える人も少なくないのではないでしょうか。本記事では、「投票の自由」と「投票の適正性」のバランスをどう考えるべきか、認知症高齢者の投票にまつわる制度や実態、そして社会的な課題について掘り下げていきます。
モヤモヤのきっかけは「この人、本当に理解できてる?」という疑問から
看護師として、病院や介護施設で高齢の方と日々関わっていると、「この状態で本当に選挙で投票って意味あるのかな…?」と感じる瞬間があります。
目の前の方は、今日が何日かも分からず、会話も断片的で、家族の名前も思い出せない。そんな状態でも「選挙権はあるから投票に行きましょう」と言われる現実。付き添い、代理投票、選挙カーの来訪対応など、職員側の労力も大きいわりに、「この人が投票で意思表示できた」と胸を張れるような実感が持てない。そんな違和感、ありませんか?
認知症でも選挙権はある──それが今の日本の法律
まず大前提として、現在の日本では認知症であっても「選挙権」は剥奪されません。
これは「公職選挙法第48条」により「選挙権は成年被後見人にも保障される」ことが明文化されているためです。2013年に最高裁が「成年後見人を理由に選挙権を制限するのは違憲」と判断して以降、制度が改正されました。
つまり、極端な話をすれば、意思疎通が困難なほど重度の認知症であっても、本人の意思確認が不可能でも、理論上は投票が可能だということになります。
代理投票制度の理想と現実のギャップ
現場でよく行われるのが、「公職選挙法第58条」に基づく「代理投票」や「点字投票」などの支援的な制度です。
この制度では、本人の意思に基づいて投票できない場合、立会人の前で意思を代弁する者(付き添い人など)が投票用紙を記入することができます。
でも実際のところ、「この人、候補者の名前すら知らないし、自分の住んでる市町村の名前すら言えない」というケースも少なくありません。
それでも周囲が「せっかくだから」「権利を行使させてあげよう」と善意で付き添って投票するのですが…正直なところ、それって本人の意思じゃないよね?と感じるケースもあります。
そこまでして投票させる意味、本当にあるの?
正直な気持ちを言えば、「そこまでして投票させる意味、ある?」と思うこともあります。
私たち看護師や介護職員が付き添いで投票所に同行するためには、移動の準備、本人の体調の把握、医療ケアの調整、万一の対応まで含めた準備が必要です。
しかも、本人が誰に入れるか分かっていなかったり、途中で「なんでここに来たの?」と混乱する場合もあるのです。それでも「選挙権があるから」と投票までこぎつけるこの構図には、ある意味の制度の美しさと現場の苦しさが共存していると感じます。
線引きは本当に必要では?モヤモヤを整理したい
制度的には「全ての国民に選挙権を」という理念があるのは理解しています。でも、医療や介護の現場では「意思の確認が取れない人にまで一律に投票させること」が、果たして民主主義にとってプラスなのかどうか、疑問に感じる瞬間がたびたびあります。
認知症が進行して短期記憶や判断力がほぼ機能していない方にも、制度上は選挙権を行使させなければならない。しかし、その投票の裏には、付き添いや代理記入者の解釈が入り込む余地があり、場合によってはその人の思想や希望が反映されてしまうリスクすらあるのです。それは当たり前のことで、認知症が中度や重度の人は周りの人がかなりサポートしないと発言すら引き出すことが難しいのです。極端な話、介助者が誘導尋問をしない限り誰にするかなんて決められない状態の人ばかりです。入れてほしくはないですが、某宗教団体の信者さんで関連する公●党に投票するというのは、それはもともと何も考えず今までも投票してきたんだろうから仕方ないかなという気持ちはごくわずかにはありますが、そういう人以外は絶対投票に強い意志も責任も何もなくやらされてるだけで意味ないです。
あとは、単なる手続きではなく、ある種の「誰が意思を決めているのか」という問題も強くあります。またこれも●明党だと思うのですが、選挙ボランティアと言って無料で選挙の付き添いや支援をしますという人たちが介護施設に来て、色々説得して投票用紙に書かせるということもあるようです。線引きや基準がなければ、制度を利用することが簡単にできてしまうのではないでしょうか。
認知症や精神疾患を理由に責任能力がないと言われる中で
選挙の投票の責任は問われない不思議
認知症や精神疾患がある人に対して、刑事責任や契約責任を問う場面では「責任能力がない」として免責されることがあります。ところが、選挙権の行使においては、同じ人々が投票できるのが原則です。この矛盾に疑問を抱く声は少なくありません。そもそも選挙の一票には、政治的な責任と判断が伴うはずですが、判断能力が低下していても制限されることはほとんどありません。
過去には成年後見制度の対象者の投票権が一律に奪われていた時代もありましたが、2013年にそれは違憲とされ、原則として投票権は保障されるようになりました。これは人権尊重の観点では前進ですが、一方で「他の責任は問えないのに、政治的判断はOKなのか」という違和感が残ります。
認知症の人から暴力を受けても、看護師や介護職員はその人は認知症だから仕方ないと我慢させられるような世界です。暴言や暴力の責任は免除されて、むしろ認知症の人に対してのプロとしての対応ができていないからだとむちゃくちゃなことを言われる中で、そんな人たちになんて手取り足取り選挙の手伝いなんてしてあげないといけないのか、絶対今の世の中のことを理解していないし、将来のことなんて考えていないし、
人権尊重、弱者を守れ!
という風潮も行き過ぎていると思います。弱者と言われるような人たちを守りすぎておかしくなっています。
私たちは、「権利」と「責任」のバランスをどこに置くのか、改めて社会全体で議論すべき時にきているのかもしれません。
法改正や基準の整備は今後の課題では?
現時点では、認知症の程度に応じて選挙権を制限するような法律は存在しません。
「成年後見人が付いているかどうか」も選挙権の制限理由にはなりませんし、公的には「本人の意思をできるだけ尊重する」ことが推奨されています。
でも、現場感覚としては、「この人に“選ぶ”という行為はできない」と感じることも多々ある。制度と現実の間で看護師や介護職員が揺れ動くこの構造は、今後、何らかの議論やルール整備が必要ではないかと感じます。
認知症でも法的には投票OK。でも、看護師としてのモヤモヤは残る
「認知症でも投票できる」
確かに法律はそうなっています。
でも、現場で目の前の人の状態を知っている看護師だからこそ、「これは本当にその人の意思なのか?」と感じる瞬間があるのです。
私たちはその違和感を無視してはいけないと思います。
制度を尊重しつつも、「本当に意味のある投票とは何か?」を、これからも現場から問い続けていく必要があるのではないでしょうか。