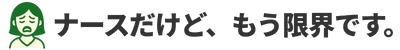看護師は仕事中に結婚指輪は外さないといけないの?
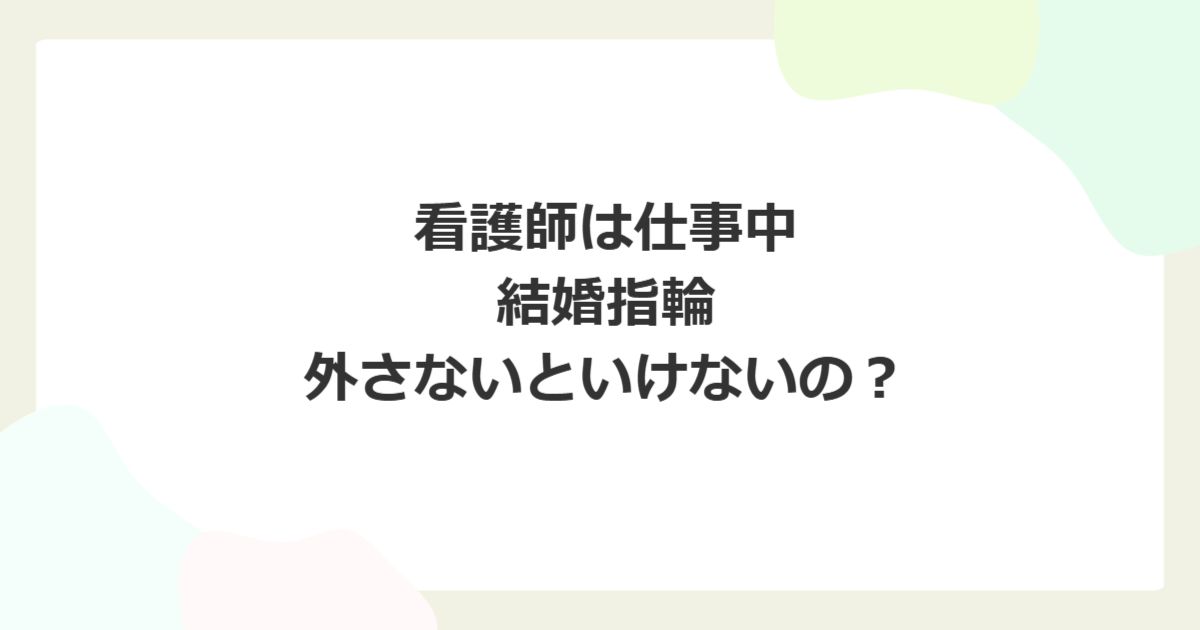
看護師は仕事中に結婚指輪をつけていてもいいのでしょうか?
「不潔に見える」「感染の原因になる」「でも外すのは寂しい」――現場では意見が分かれるテーマです。
病院によっては指輪の着用を禁止しているところもありますが、訪問看護などでは許可されている場合もあります。
この記事では、医療現場で結婚指輪がNGとされる理由や、実際の看護師たちの声、外来・病棟・訪問看護それぞれの違いについて詳しく解説します。
清潔・安全・信頼のバランスを考えながら、自分らしい判断をするためのヒントをお伝えします。
清潔・感染管理の観点から見る「指輪NG」の理由
看護師が結婚指輪を外すかどうか——これは職場によって意見が分かれるテーマです。
病院勤務の看護師であれば、基本的には「つけない」方が多いのが現状です。理由は、感染管理の観点からです。看護師の「手」は、あらゆる処置やケアを通して多くの人に触れます。そのため、常に「自分の手は感染源になりうる」という意識を持つことが職業倫理として求められています。
指輪の下はどうしても洗浄が不十分になりやすく、雑菌が残ってしまうことがあります。消毒や手洗いをしても、指輪と皮膚の間に水分や細菌が溜まり、不潔な状態を生みやすくなるのです。
「指輪をしている手=不潔な手」と判断されることもあり、感染防止を最優先する医療現場では、結婚指輪を含むアクセサリーの着用を控えるよう指導されることが多いです。
大切な結婚指輪だからこそ、仕事中にはつけないという考え方もあります。清潔を守ることが患者さんの安全につながると考える看護師は多く、指輪を外してロッカーにしまっている人も少なくありません。
職場による違いもある、外来・オペ室・病棟での対応
勤務先によっても対応は異なります。
たとえば手術室(オペ室)勤務の看護師は、清潔操作が厳密に求められるため、当然ながら指輪の着用は禁止です。外来や一般病棟でも「原則外す」職場がほとんどですが、なかには結婚指輪に限って許可されている場合もあります。
一方で、内科医などは診察時に指輪をしていることもありますが、外科医は手術に関わるため、診察中であってもつけないことが多いようです。つまり「手をどの程度清潔操作に使うか」で、ルールが変わってくるといえます。
指輪を通したネックレスならOK?職場ルールと代わりの方法
結婚指輪を職場でつけられない代わりに、ネックレスに通して身につける看護師も多くいます。
ネックレスであれば手洗いや処置に支障がなく、指輪を失くす心配も少ないため、代替手段として人気です。実際、控えめなアクセサリーならOKとしている病院や訪問看護ステーションもあります。
一方で、揺れるタイプのアクセサリーや長いネックレスは、患者さんに触れたり、ケア中に引っかかったりするリスクがあるため避けた方が安全です。あくまで「清潔で控えめ」が基本。医療現場では「華美にならない範囲で身だしなみを整える」という感覚が求められます。
訪問看護では事情が少し違う
訪問看護では、病院とは異なり、患者さんの「自宅」という生活の場にお邪魔します。
そのため「利用者や家族がどう感じるか」が大切になります。
多くの訪問看護ステーションでは、控えめなネックレスや小ぶりのピアス、結婚指輪を認めているケースもあります。利用者や家族から特に不潔感を指摘されることはほとんどなく、「マナーとして清潔感があればOK」という雰囲気のところも多いようです。
また、訪問看護ではセクハラ対策の一環として、あえて結婚指輪を身につけて「既婚者である」ことを示すケースもあります。
とはいえ、利用者の性格や家庭環境によって印象が変わるため、最初は外しておき、信頼関係ができてから身につけるなど、状況に応じた判断が求められます。
清潔・安全・信頼のバランスを大切に
結婚指輪をつけるか外すかは、職場のルールと自分の価値観のバランスで決めることが大切です。
感染管理を徹底する病院では「外す」が基本ですが、訪問看護のように柔軟な現場では「信頼関係を損なわない範囲でつける」ことも選択肢になります。
大切なのは、指輪の有無よりも「患者さんにとって清潔で安心できる看護を提供できているか」という点です。
結婚指輪は愛の証でありながら、看護師にとっては職業倫理や信頼の象徴でもあります。
その意味を大切にしながら、自分に合ったスタイルを選ぶことが、プロとしての美しさにつながるのではないでしょうか。